 ダンドリーナ
ダンドリーナ「帰ってきたらゲームばかり…」
「明日の準備、また言わないとやらない…」
子どもが“自分から動いてほしい”
と願うママはたくさんいます。
だけれども
怒るたびに罪悪感が残って
ますます気持ちがすれ違っていく…。
この記事では
タイムクリエイトlabの受講生
智美さんが実践した
「ルーティンの分解」で
子どもが自然に行動できるようになった方法を
具体的なステップとともにご紹介します。
“言わなくても動ける子”に育てる秘訣
それは、子ども目線の「仕組み作り」
から始まります。
この記事のハイライト
ゲームばかりの子どもが、自分で動けるようになるには?
答えは「ルーティンを分解して、迷いをなくす」ことでした。
親子でつくる仕組みが、毎日をラクに笑顔に変えてくれます。
なぜ子どもは動かないの?ママの理想と現実のギャップ


“当たり前にできるはず”と
思っていたことが
実はハードルだらけだったんです。
智美さんはフルタイム勤務で
朝6時半出発・夜6時半帰宅。
祖父母が子どもたちの面倒を
見てくれてはいるものの
学校の支度や宿題はノータッチ。
帰宅すると
リビングにはゲーム中の兄弟が…
ぬぎっぱなしの服
開けっぱなしのランドセル。
「明日の支度は?」
「ゲームばっかりじゃない!」
毎晩、そんな声を張り上げる日々。
「夕飯も遅くなるし
怒りたくないのに怒ってしまう…」
ママもクタクタ、子どもも不機嫌。
まさに負のループに陥っていたのです。
気づきのきっかけ:できないのは「意志」ではなく「設計」のせい


できないのは「やる気」ではなく
「どうやるか」が
わからなかっただけかもしれません。
タイムクリエイトlabの講座で
智美さんはこんな話を聞きました。
「小学3年生の男の子が、一人でカレーを作るようになったんです」
驚きと同時にふとよぎったのは
「うちの子にはムリ」という諦め。
だけれども
その子も最初は
“できなかった”ところから
スタートしていたのです。
鍵になったのは
「家事を分解する」こと。
動きが“迷い”によって止まる前に
手順を“見える化”してあげる。
その工夫こそが
子どもの行動を変えてくれるのです。
子どもが変わる!ルーティン分解4ステップ
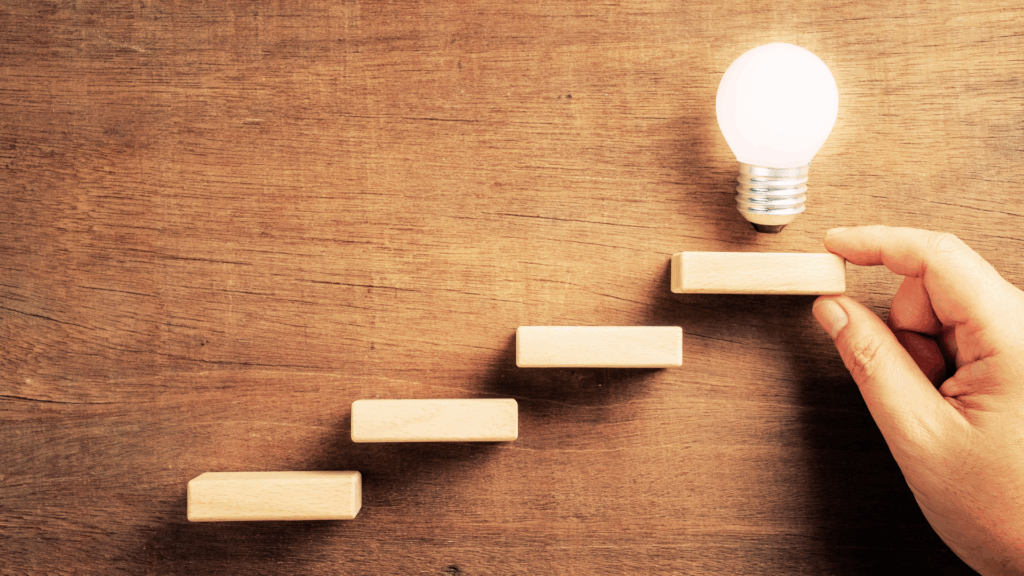
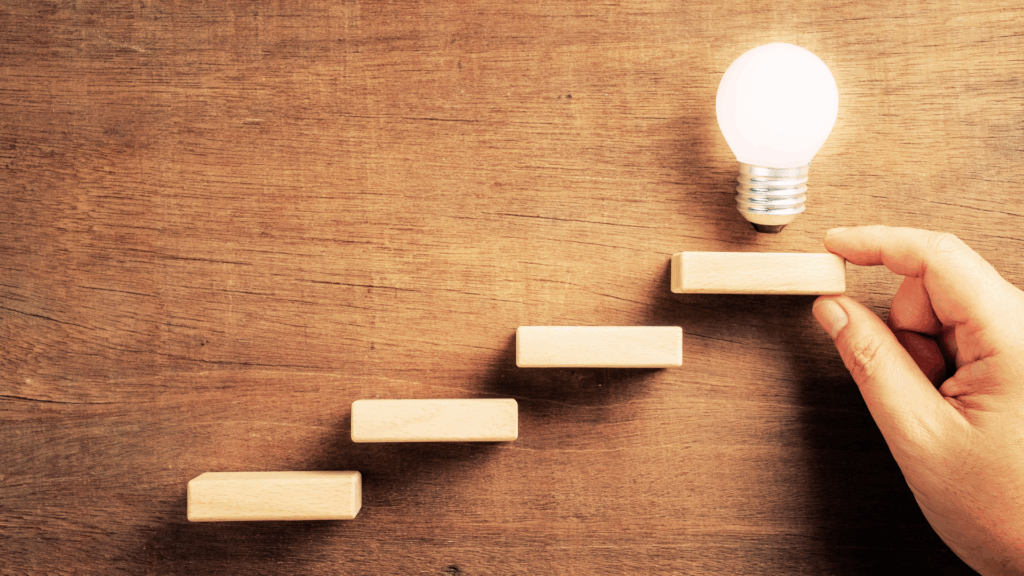
子どもが動けない理由と
動けるようになる仕組みを
順番に見ていきましょう。
① ゴールを決める
子ども:帰宅後
自分で洗い物と支度が完了できる
ママ:寝る前に30分、笑顔で親子時間をとる
② 問題点を洗い出す
- 何をすべきかが明確でない
- ゲーム環境が整いすぎて誘惑が強い
- 支度の動線が遠くて面倒に感じる
- 見守る大人が甘やかしてしまう環境
③ 行動を分解する
- 靴を脱ぐ
- 上着を定位置にかける
- ランドセルを開けて中身を出す
- 体操服・給食セットを洗濯かごへ
- お箸・コップを洗って拭く
- 明日の準備をセットする
💡ここでのポイントは
「1つ1つが迷いなくできるようにする」こと。
④ 実践×仕組み化
▶ 子ども専用ランドリーボックスをリビングに設置!
→ 動線を短くし、行動のハードルを下げる
▶ ママの想いを子どもに「伝える」
「早くご飯が食べられたら、お楽しみ時間ができるよ♪」
“ただの指示”ではなく、“楽しみ”につなげた提案が子どもの心を動かしました。
子どもは「理由」がわかると、動ける


子どもが動けない理由と
動けるようになる仕組みを
順番に見ていきましょう。
「なんでこれをやるの?」がわかると
子どもは前向きに行動します。
たとえば
「ママが帰ったときに準備が終わってると
早くご飯が食べられるよ」
「そしたらブロックもゲームも
ゆっくり楽しめるね」
こんな風に“やる意味”がわかると
子どもたちは自然とスイッチONに。
自分からゲームをやめて
食器の配膳もしてくれるように!
「できなかった」が「できた」に変わる!その瞬間が自信になる


「やってみたらできた!」という経験が
自己肯定感をグッと育ててくれます。
最初は一緒に。
けれども、手順が身につくと
徐々に1人でできるようになる。
そうやって“習慣”が
できあがっていくのです。
そして何より大切なのは
「ママの言葉が届いた」という実感。
信じて任せてくれた
その想いが、子どもの自信になります。
「じゃあどうする?」が自立を育てる魔法の言葉


正解を与えるのではなく
一緒に考えるプロセスが
子どもを大きく成長させます。
失敗してもいい。
できなくても責めない。
大切なのは
「できなかった時にどうするか」を
一緒に考えること。
「じゃあどうする?」を繰り返すことで
子どもは「自分で考えて行動できる力」を
少しずつ育てていきます。
“自分から動ける子”は、ルーティンで育てる!


ルールではなく“ルーティン”が
子どもに安心感と自信をもたらします。
帰宅後のルーティンを
“分解”して“見える化”してあげること。
そして“できる未来”を一緒に描くこと。
それが
子どもの「自分から動く力」を
育てる最短ルートです。
お楽しみ時間
配膳のお手伝い
早めの夕飯。
どれも
「子どもの未来へのギフト」になります。
よくある質問(FAQ)
- 子どもがまったく話を聞いてくれないのですが、ルーティンは通用しますか?
-
はい、ルーティンは「伝え方」と「仕組み方」で変わります。
大切なのは“親の理想を押しつける”のではなく、
子ども自身が「やってみたい」「できそう」と思えるように設計すること。
まずは1つ、できそうなことから一緒に決めて始めてみましょう。 - 小学生低学年でもルーティンは覚えられるんですか?
-
もちろんです!
「やること」を分かりやすく視覚化(チェックリストやイラスト)すると、
年齢に関係なく自然と習慣にしやすくなります。
“考えなくても体が動く”を目指して、シンプルな設計がコツです。 - ゲームをやめさせるにはどうしたらいいですか?
-
無理にやめさせるより、「やってからゲーム」→「やってもゲーム」→「やらないと楽しめない」という
“順番のスイッチ”が効果的です。
楽しみを禁止せず、ルーティンの先に「お楽しみ時間」を設定すると、自然と行動が変わってきます。 - 兄弟で行動に差がある場合はどうすればいい?
-
比べるのではなく、それぞれに「できる工程」を用意してあげましょう。
年齢や性格によって“できるステップ”は異なるため、個別のルーティンを作るのがおすすめ。
お兄ちゃんには自分の支度、弟にはランドリーボックスへの配達係など、役割分担も◎ - 最初の一歩としておすすめのルーティンはありますか?
-
「帰宅後の5分ルーティン」がおすすめです。
上着をかける・ランドセルを開ける・体操服を出す…この流れだけでも、
“自分でできた!”という体験が子どもを前向きにしてくれます。
まずは“ひとつできた”の積み重ねからスタートしましょう。
この記事のまとめ


子どもが動かないのは
「意志の弱さ」ではなく
「仕組みが足りないだけ」。
行動を分解して
ゴールを共有して
少しだけ環境を整える。
たったそれだけで
子どもは自分で考えて
動けるようになります。
毎日イライラしていたママも
怒らずに見守れるように変化しました。
“できない”を“できた!”に変えるのは
「言葉」ではなく「仕組み」。
ルーティンは
子どもとママの未来を
優しく変えてくれる魔法です。
あなたのご家庭にも
今日から小さな一歩を
取り入れてみませんか?
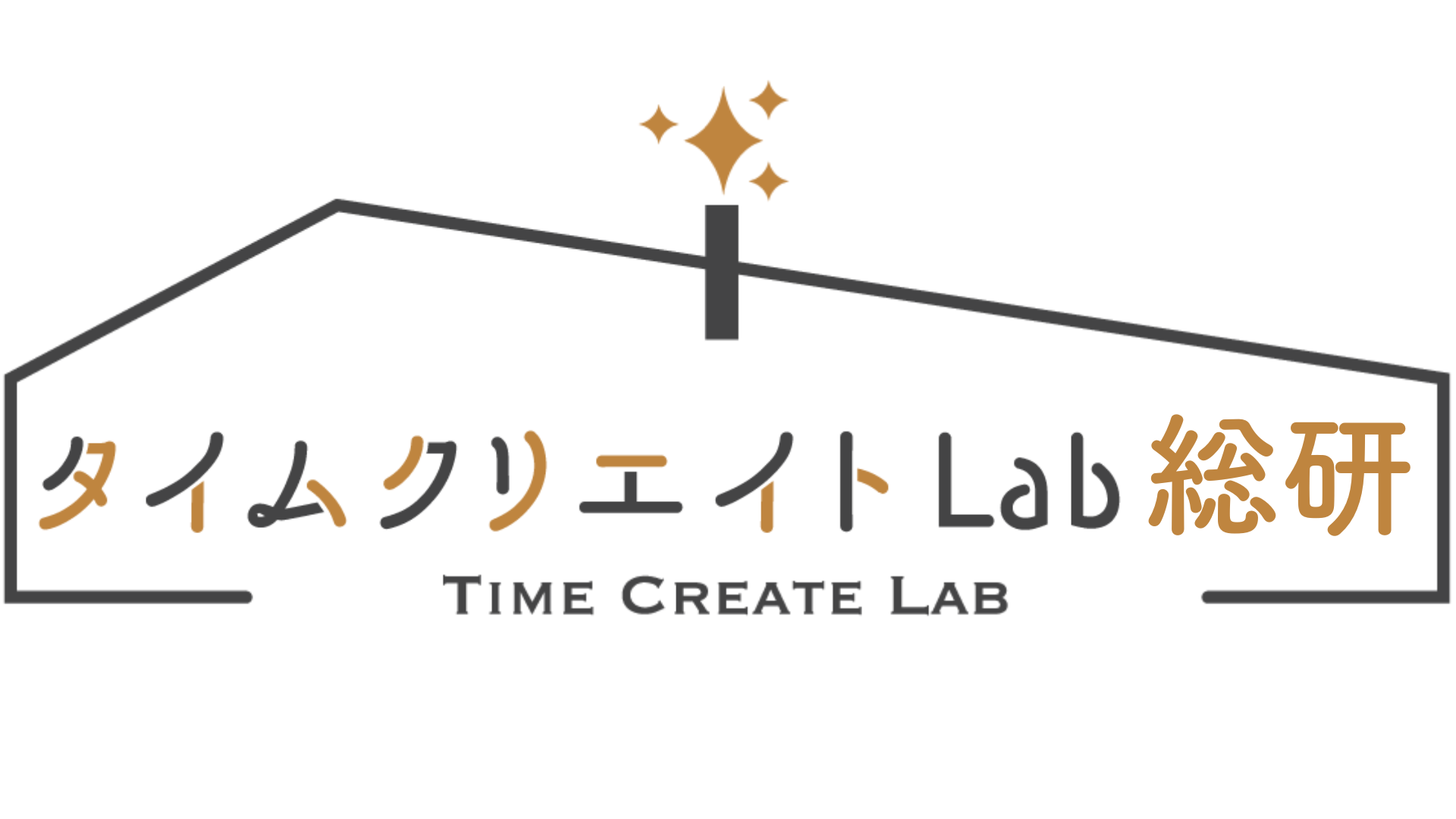






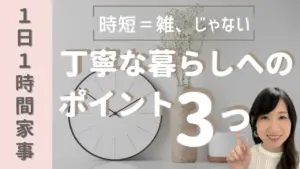

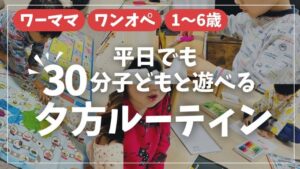

コメント