子どもが床に寝転んで泣きわめき、
必死に声をかけても何も届かない。
そんな「癇癪育児」の真っ只中で、
あなたは今日も、ひとりで悩んでいませんか?
 ダンドリーナ
ダンドリーナ「つい怒ってしまった…」



「また、言いすぎたかもしれない…」
けれども安心してください。
癇癪は“しつけの失敗”ではなく、
“感情の未熟さ”の現れ。
その関わり方をほんの少し変えるだけで、
子どもとの関係も、
自分の気持ちもラクになっていきます。
この記事では、
【癇癪を起こした子どもへの接し方】と
【親自身の気持ちの整え方】を、
リアルなママたちの声とともに、
やさしくお届けします。
ハイライト
🔸この記事のポイントはこの3つ!
- 癇癪中の子どもには声が届かない
→落ち着くまで「そっと離れる」のが効果的 - 癇癪後こそ“話を聞く”が信頼を育てる
→説得より、共感と観察がカギ - ママの心の余白が、育児の余裕につながる
→怒りの裏にある感情をノートに書くだけでOK
はじめに:その「癇癪対応」、がんばりすぎていませんか?


育児の中でもとくに心を削られるのが、
子どもの癇癪。
イヤイヤ期だけでなく、
年中・年長・小学生になっても続くことがあります。
「癇癪 育児 疲れた」
で検索するママが増えているのは、
それだけ一人で抱えている方が多い証拠です。
この記事では、
✅癇癪を起こした子どもへの接し方
✅ママ自身の心の落ち着け方
✅癇癪が起こる理由と予防法
を、実際のママたちのリアルな声とともにまとめています。
癇癪の時、子どもは“聞こえていない”と知っておく


癇癪を起こしている子どもには、
どんな声も届かないと理解することが第一歩です。
癇癪中の子どもの脳は“パニックモード”
泣き叫び、暴れて、話が通じない。
そんな時、
子どもの脳は「理性オフ・感情100%」の状態です。
このときの子どもには、
✅話しかけても聞こえていない
✅共感も説明も、届かない
つまり、「説得しよう」と頑張るほど、
親も子も苦しくなってしまうのです。
癇癪の対応は“その場で落ち着かせようとしない”
こんな声があります。



「うちでは、癇癪が始まったら“離れる”ようにしています。
『10分経ったら戻るね』と言って、別室に行くと、自然に落ち着くことが増えました」


子どもの感情が落ち着くまで
そっと距離をとることが、
結果的に早く気持ちが戻るコツなのです。
癇癪が落ち着いた後に、何をする?


癇癪が収まったタイミングこそ、
子どもの心に寄り添うチャンスです。
まずは「話を聞くだけ」でOK
癇癪の嵐が過ぎたら、
穏やかなタイミングを見計らって声をかけます。
✅「どうして怒ってたのかな?」
✅「ママが聞いてもいい?」
ここでは、
否定しない・ジャッジしない・共感だけがポイントです。
子どもの言葉を“観察”してみる
あるママはこう話します。



「息子が『2回言わないで!』『急に言わないで!』と教えてくれていました。最近は“取り扱い説明書”を作ってます」
このように、
子どもが自分の気持ちを言語化できる瞬間を拾っていくと、
癇癪が起きる前兆や
スイッチも見えてきます。
“癇癪育児”で疲れたママが、まずやってほしいこと


自分の感情を整理することで、
癇癪育児のストレスは軽くなります。
「怒りの構造」を紙に書いてみよう
感情にのまれると、自分の思考のクセに気づけません。
そこでおすすめなのが、
スケジュール帳やノートを使った「怒りの棚卸し」です。
✔ どんな場面で怒った?
✔ その裏にある「〜すべき」の思い込みは?
✔ それは本当に必要?重要?
こうして見える化することで、心の余白ができてきます。
📖参考図書:
アンガーマネジメントトレーニングブック2025年版
自分を整えることが、家族の心を守る
あるママの声:



「娘の癇癪に巻き込まれてたけど、泣き時間をタイマーで計るようにしたら、私の気持ちが客観視できて楽になった」



「帰宅前に“この後どうしたいか”を子どもと話しておくようにしたら、少しずつ落ち着いてきた」
癇癪は“習慣”にもなり得ます。
だからこそ、
親の心の整え方もセットで育てていく
ことが大切なんですね
癇癪を乗り越えるには、“完璧な親”を目指さないこと


癇癪育児に大切なのは、
理想の親よりも“リアルな共感”です。
癇癪が起きたときに



「またダメだった」



「ちゃんと向き合えてない」
と自分を責める方も多いです。
けれども——
子どもは、
完璧な対応よりも、“自分を大切にしてくれる人”
を見ています。
あるママの言葉が、
きっと支えになるはずです。



「うちの娘も癇癪すごいです。上手くいく日もあれば、そうでない日もありますよね。お互い気晴らししながら、ゆっくり進んでいきましょう」
✅【FAQ(よくある質問)】
- 癇癪のとき、親はどう対応すればいいですか?
-
癇癪中の子どもは理性が働かず“感情の嵐”の真っ只中にいます。
このタイミングで説得したり叱ったりしても効果は薄く、むしろ悪化することも。
まずは距離をとって「落ち着いたら戻るね」と伝え、子どもも親も一度クールダウンすることが大切です。 - 癇癪後、子どもにどう声をかけると良いですか?
-
癇癪が収まったあとが“心を育てるゴールデンタイム”。
「どうして怒ってたの?」と優しく問いかけ、子どもの話に耳を傾けてあげましょう。
否定せず、共感するだけで、子どもは“わかってもらえた”と感じ、安心感につながります。 - 癇癪が起きる前に予防できる方法はありますか?
-
癇癪のきっかけには「急な変化」「予想外の声かけ」「眠気・空腹」などが多くあります。
事前に「この後どうするか」を共有したり、子ども自身に選択させたりすることで、予防につながることが多いです。 - 癇癪対応に疲れて、自分を責めてしまいます…
-
それは多くのママが感じていることです。
「完璧な対応」は必要ありません。
怒ってしまった日も、自分を責めず「今日はできたことに目を向ける」だけでも、心は整っていきます。
まずはご自身の感情を、ノートやアプリに書き出してみるのがおすすめです。 - 癇癪が多いのは発達の問題でしょうか?
-
癇癪は多くの子どもが経験する“発達の一過程”です。
ですが、極端に頻度が高かったり、日常生活に大きな支障が出ている場合は、専門家(小児科医・カウンセラー)に相談してみるのも一つの手です。
家庭での対応だけで抱え込まず、必要に応じてサポートを受けることは、親子どちらにとっても良い選択です。
🌿まとめ


癇癪のたびに
「また怒っちゃった」と自己嫌悪していた日々。
けれども、
子どもは“完璧なママ”より
“自分を見てくれるママ”が好き
なんです。
癇癪中は“声が届かない時間”と割り切って、
終わったあとに
「聞く」「観察する」「寄り添う」——
この3つを意識するだけで、
親子の関係はぐっと近づいていきます。
そしてなによりも大切なのは、
ママ自身が自分を大切にすること。
怒りや疲れを
ノートに書き出すことからでいいんです。
ほんの少しの習慣で、
育児はもっとラクになります。
「癇癪に疲れた日こそ、自分を責めないであげてくださいね」
🎁もっと手帳術を深めたい方へ|無料小冊子プレゼント中!
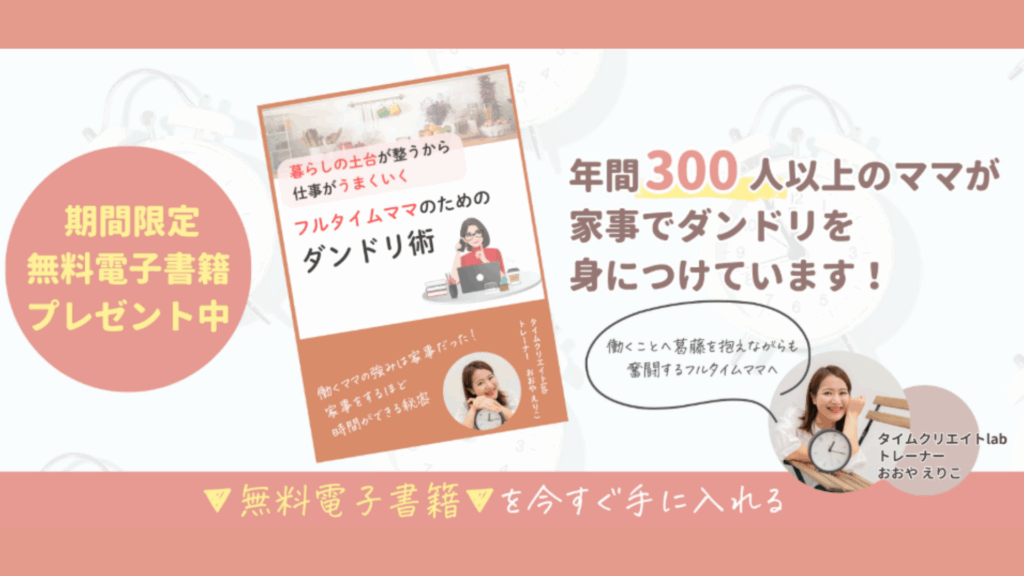
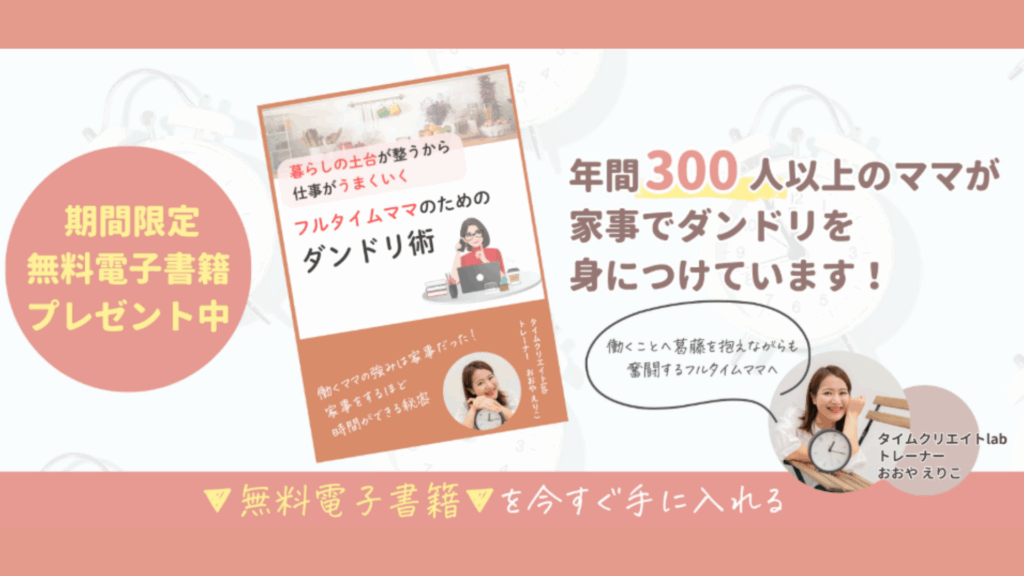
「また怒っちゃった」
と自己嫌悪していた日々は
むしろ、がんばっていた証拠だった。
そこに気づいた時、
自分を責める気持ちがスッと消えて、
「今できることを大切にしよう」
って思えるようになりました。
\今だけ限定!手帳と仲良くなるきっかけをあなたへ/
『暮らしの土台が整うから仕事がうまくいく フルタイムママのためのダンドリ術』
を無料でプレゼント中!
『暮らしの土台が整うから仕事がうまくいくフルタイムママのためのダンドリ術』
もう怒らない自分になれる!
ママの気持ち整理術も紹介している1冊です。
【子どもの癇癪に疲れたママへ贈る言葉】癇癪に振り回されず、親子で気持ちを育てる毎日へ


あなたの今日のがんばりが、
いつかきっと「親子の信頼」に変わります。
焦らず、比べず、ほどよく。
ママの笑顔は、
家族の未来を照らします♡
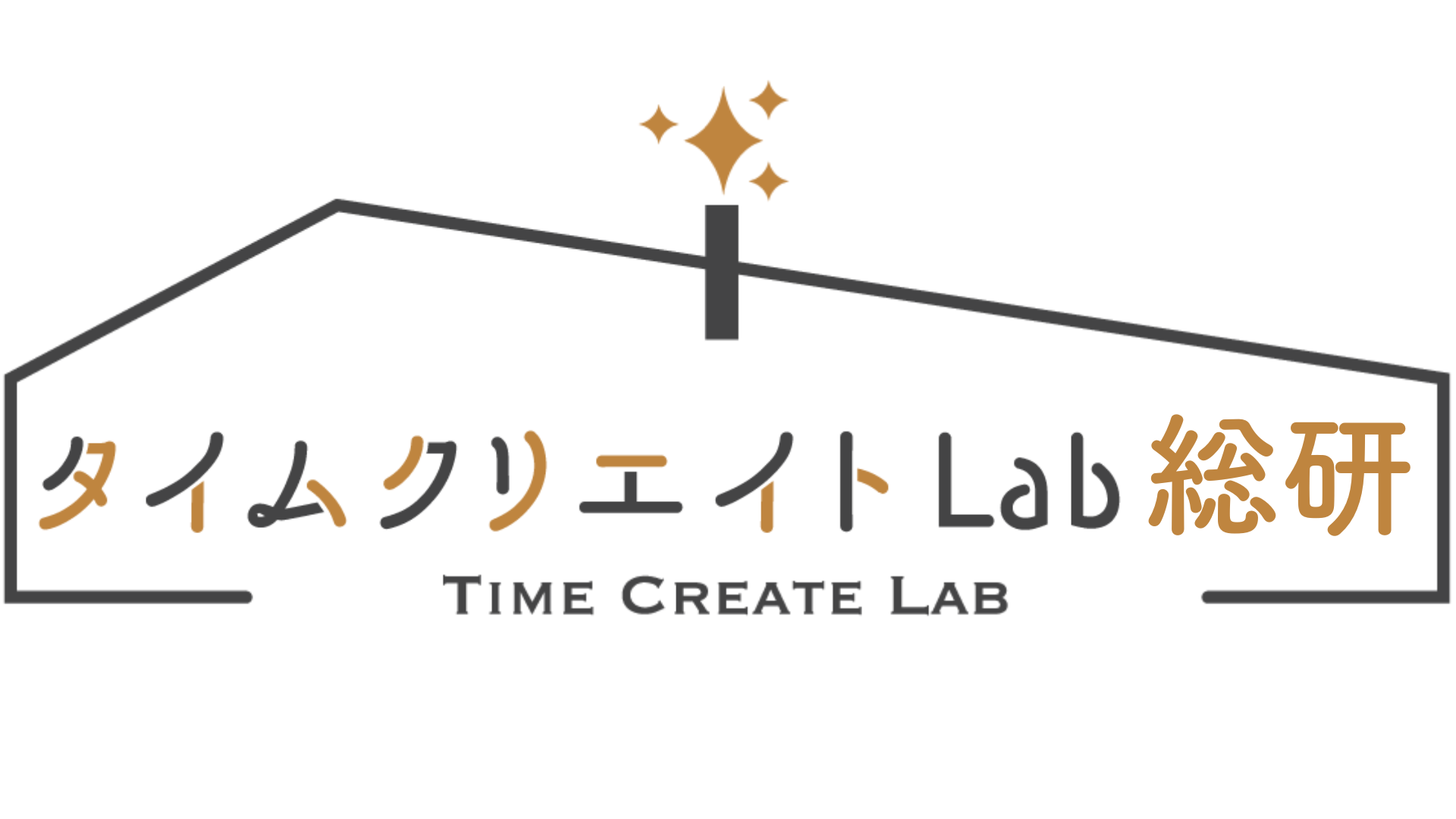
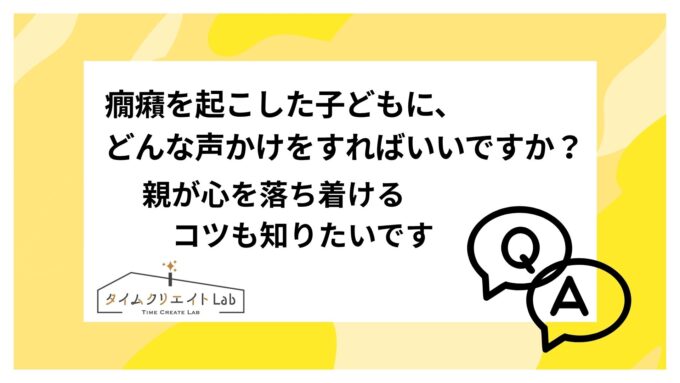






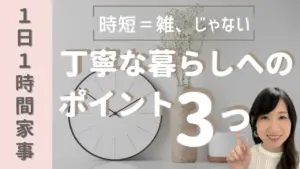


コメント