「小さい子でも、なにかお手伝いさせたいけれど…まだ早いかな?」
そう悩むママへ。
実は、0歳からでも“家のおしごと”に関われる方法があるんです。
お手伝いは、単に家事を助けるだけではありません。
子どもの「できた!」という喜び、自信、
そして親子のあたたかい時間を育ててくれる大切なコミュニケーションです。
この記事では、
小さな子でもできる具体的なお手伝いの方法と、
うまく続けるためのコツをご紹介します。
ハイライト
✓小さい子でもできる“お手伝い”は0歳から始められる
✓「ごはんを炊く」などの家事はステップに分ければ参加可能
✓最初は1ステップだけでもOK。声かけがやる気の鍵になる
✓お手伝いを通して“自己肯定感”と“家族の絆”が育まれる
✓今だけ!家事を1時間で終わらせる無料プレゼントもあり🎁
A:もちろんあります!0歳からでも“おうちしごと”を通して家族の時間を育てられますよ。

「うちの子、まだ1歳なんだけど…」というママへ
「お手伝いってもうちょっと大きくなってからじゃない?」
そんなふうに思っていませんか?
けれども実は、お手伝いは0歳からでもできるんです。
まだ言葉も少ない時期でも、“やってみたい!”という気持ちはちゃんと育っています。
はじめは“おしごとごっこ”のような気持ちでOK。
親子の関係をもっと豊かにしてくれる、小さい子のはじめてのお手伝いをご紹介します。
🍚たとえば「ごはんを炊く」を分解すると…
普段私たちがサラッとやっている“ごはんを炊く”という家事。
でもこの工程を分けてみると、こんなにたくさんあります。
- ザルを出す
- お米をはかる
- お米をとぐ(洗う)
- お水を入れる
- 炊飯器にセットする
- スイッチを押す
この中で、たった一つだけをお願いすることから始めれば大丈夫!
たとえば…
「ママが出したお米カップ、渡してくれる?」
「スイッチ、ポチって押してみる?」
…これだけでも、子どもにとっては立派なお手伝いです。
小さい子にお手伝いを頼むメリットは?
小さい子にお手伝いをお願いすると、正直ちょっと手間がかかることもあります。
けれども、そこから得られるメリットはたくさん!
✓自己肯定感:「できた!」の体験が自信に
✓ 家族の絆:「ありがとう」と伝え合える関係に
✓習慣化:「家のことは、みんなでするもの」という意識に
大切なのは、“完璧にやること”ではなく“関わること”。
手伝うことで「自分は役に立てる存在なんだ」と感じられると、
子どもはどんどん表情を変えていきます。
声かけのコツ:お願いじゃなくて、信頼して「任せる」
小さい子に何か頼むとき、
「やってみる?」よりも効果的なのがこんな言葉です。
「〇〇ちゃんがやってくれたら、ママ助かるなぁ〜!」
このひと言だけで、子どもは“頼りにされている”と感じて、
張り切ってくれます。
お手伝いが終わったら
「わぁ〜、ありがとう!すっごく助かった!」
と、感謝の気持ちを言葉で伝えることも忘れずに。
「うまくいかない…」ときの対処法
もちろん、毎回うまくいくとは限りません。
気分が乗らない日もあるし、
途中で水をこぼしてしまうことだってあります。
そんなときは、責めたり怒ったりせずに
「一緒にふこうか!」「お水、もう一回いれてみよっか」
とゲーム感覚で巻き込んでしまうのがおすすめです。
0歳からできる「おしごとごっこ」の例
- おむつポーチを渡してもらう
- 洗濯物をかごに入れる
- ティッシュを取って渡す
- タオルを畳むのをマネしてみる
- 食卓にスプーンを並べる
最初は時間がかかっても、
「ありがとう」の積み重ねが、子どもを育ててくれます。
なぜ“今”から始めるのが大切なの?
親がなんでもやってしまうと、子どもは“待つ側”になってしまいます。
けれども早くから関わることで
「自分のことは自分で」「人の役に立てる」
という力が、自然と身についていきます。
おうちしごとは、
“生活力”と“思いやり”を育てる教育の場でもあるのです。
そして今だけ、
【時短家事が続かないママへ】
「家事を減らさず、1時間で終わる仕組み」の
無料プレゼントをご用意しました✨
まとめ

「まだ小さいから無理」と決めつけず、“できることだけ1ステップ”から始めてみませんか?
お手伝いは、毎日の家事が“育ちの場”に変わる魔法の時間です。
小さい子の「やってみたい!」を大切に育てることが、将来の“自立心”や“家族との絆”に必ずつながっていきます。

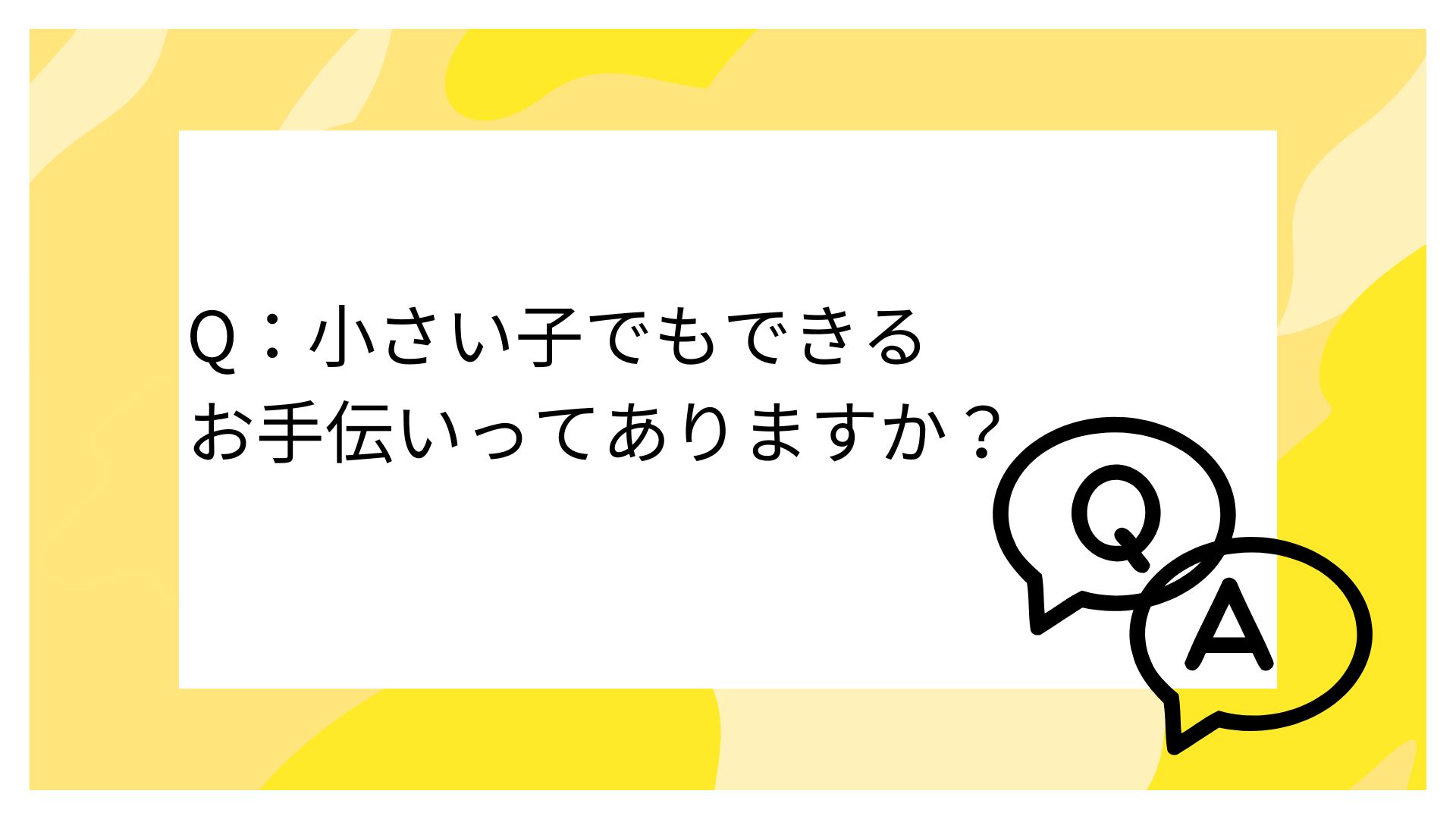


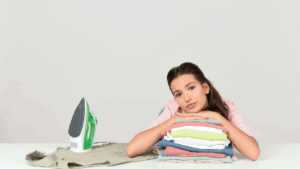
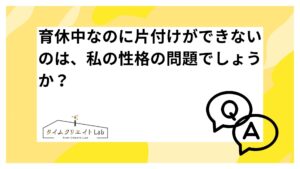
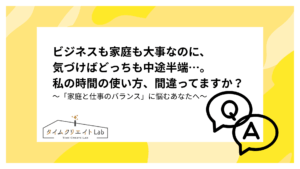
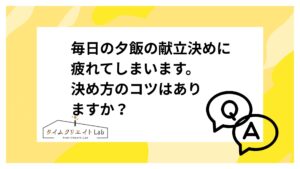
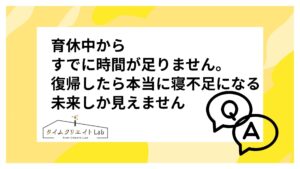
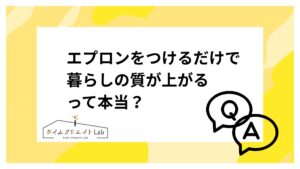
コメント