「どうして、うちの子はお手伝いをしてくれないの?」
そう悩むママはとても多いです。
「ご褒美で釣るのはちょっと違う気がする…」
「けれども、全然動かない…」
そんなモヤモヤを抱えているあなたへ。
この記事では、
実際に子どもが自分から家事に関わるようになったご家庭の工夫を、
リアルな体験談と共にご紹介します。
ご褒美やお小遣いに頼らず、
子どもの“やってみたい”を引き出す7つの方法を知れば、
今日から声かけが変わりますよ✨
ハイライト
子どもがお手伝いしてくれない…
声をかけても「イヤだ」と言われる…。
そんな毎日を卒業したいママへ。
自主的に家事に参加する
“きっかけ”は、
ちょっとした声かけと環境の工夫でした。
「やらせる」ではなく「やりたくなる」家事を目指して

「うちの子、どうしてお手伝いしてくれないんだろう?」
そんなふうに悩んだことはありませんか?
頼んでもイヤイヤ、やっても長続きしない…。
ご褒美をあげるのも抵抗があるし、
かえって依存しないかも心配…。
実は、お手伝いが“習慣”になっている家庭には、
ちょっとしたコツがありました。
ここでは、ママたちのリアルな体験談をもとに、
子どもが「自分から」動いてくれる7つのヒントをご紹介します。
子どもが自主的に家事を始める7つのヒント

1. 興味からスタート!「ちょっとやってみる?」が効く
最初から「これやって」と任せるのではなく、
まずは興味を引くことから !
料理中に「お味見してみる?」
「この野菜、触ってみる?」と声をかけると、
「やってみたい!」が自然と生まれます。
一度やって楽しかった体験は、次の行動につながります。
2.「ありがとう」「助かったよ」がやる気の源に
お手伝いの後は、
しっかりと言葉で伝えることが大切です。
「ありがとう!助かったよ」
「ママ、うれしかった!」
こんなふうに気持ちを伝えることで、
子どもは“やってよかった”という成功体験を得られます。
2歳の子でも「ママ見て!」と
ニコニコしながら報告してくれるようになりますよ。
3. 得意なこと・好きなことから始める
子どもにも「得意・不得意」があります。
それを上手に活かすのがコツ。
- 並べるのが好きな子 → おもちゃの整理整頓
- 料理に興味がある子 → 一緒にクッキング
- 工作好き → 洗濯たたみや小物整理
「できた!」という自信が、
自発的な行動を後押しします。
4. シールやスタンプで“楽しく習慣化”
紙にマス目を書いて、シールを貼っていく「お手伝いカード」もおすすめ。
シールを貼りたくて「これやるー!」と自分から言ってくれるように。
全部埋まったら「一緒におやつを買いに行く」など、
ささやかな楽しみを用意すると、習慣になりやすいです。
5. ポイント制度は“きっかけ”として活用しよう
「1回のお手伝いで1ポイント」
「10ポイントたまったら100円と交換」など、
ルールをシンプルに。
さらに、自分からやってくれた時は
「ダブルポイント!」と特別感を演出。
報酬が目的になるのではなく、
「褒められた体験」こそが残ります。
6. タイミングは“甘えてくる時”がチャンス!
子どもがかまってほしい時、
まとわりついてくる時がチャンス。
「じゃあ、一緒におにぎり握ってみる?」
「味見してもらえるかな?」
さりげなく巻き込むことで、
自然と家事に参加してくれるようになります。
7. 最初のハードルは“低く・簡単に”
初めてのことには慎重な子も多いので、
「絶対できるレベル」のお手伝いから始めましょう。
「お箸を並べる」
「エプロンをたたむ」
「お味噌汁をお願い!」など、
“できた!”という成功体験を重ねていくことが、
自信につながります。
Q. ご褒美をあげすぎると依存しませんか?ご褒美ってどこまでOK?

A. ご褒美は「始めるきっかけ」として活用すればOKです。
ただし、
ご褒美だけで完結させないことがポイント。
「ありがとう」
「ママすごく助かったよ」
「あなたがいてくれてうれしい」
こうした言葉をセットで伝えることで、
“誰かの役に立てた”という感覚が子どもに残ります。
まとめ||“できたよ!”が子どもの心を育てる

お手伝いは、ただの作業ではなく、
子どもにとって「自分の役割を実感できる時間」です。
最初はうまくできなくても大丈夫。
できたことを喜び合うことで、自然と習慣になっていきます。
ママの「ありがとう」が、子どもの背中をそっと押してくれる。
そんな優しいお手伝いタイムを、今日から始めてみませんか?
🎁特典プレゼントのご案内
|「お手伝い 子ども」で調べてもできなかったママへ
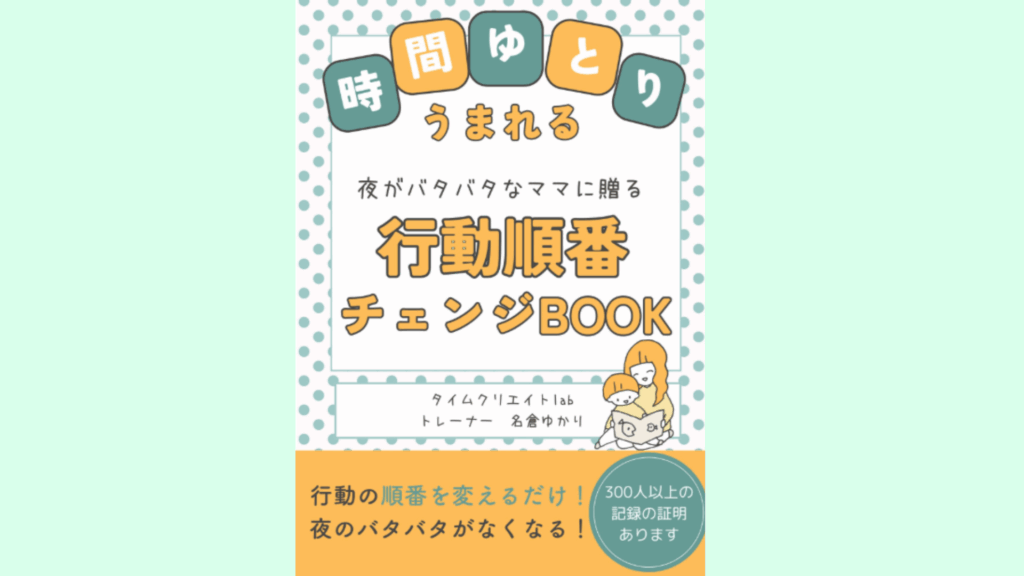
\今だけ無料プレゼント中!/
『行動順番チェンジブック』
子どもが“自ら動きたくなる”家庭の工夫が詰まった1冊。
どう声をかければよいか、何を変えればいいかがわかります!
❓よくある質問
- お手伝いしてくれないとき、どう対応すればいい?
-
無理にやらせようとせず、「興味のきっかけ」を探してみてください。
子どもが拒否するのは、“やらされ感”や“できなさそう”という不安があるから。
まずは「見てるだけでもいいよ」「ママがやるから見ててね」と、安心できる声かけをしてみましょう。
好奇心が芽生えるタイミングを見逃さないことが大切です。 - お小遣いやポイント制は、甘やかしになりませんか?
-
目的が「依存」ではなく「自信づけ」であれば問題ありません。
最初はご褒美やポイントが動機になっても、
その後「ありがとう」「ママ助かったよ」と感謝を伝えることで、
“人の役に立つって嬉しい”という体験が残ります。
それが自主性へとつながっていきます。
- 下の子ばかり巻き込まれて、上の子が乗ってこない…
-
年齢によって関わり方を変えてみましょう。
小さい子は一緒に体験するのが楽しく、大きい子は「任されること」が嬉しい年頃。
「お味噌汁お願いね」「○○って野菜、どんな料理に合うと思う?」など、
“責任ある役割”を渡すことで上の子も巻き込めます。 - 続かない時はどうすればいいですか?
-
できたことにフォーカスして、小さな成功を積み重ねましょう。
毎日やらせる必要はありません。
「昨日できたね」「ありがとう!また今度お願いしてもいい?」と、
やった事実を丁寧に振り返っていくことで習慣化に近づきます。 - そもそも何歳くらいからお手伝いって始められる?
-
2〜3歳から“巻き込み型”でスタートできます。
たとえば「お箸を運んでね」「テレビの電源を切って」など、
簡単な動作から始めてみましょう。
「できたね!」の経験が増えると、どんどん自分から動けるようになります。

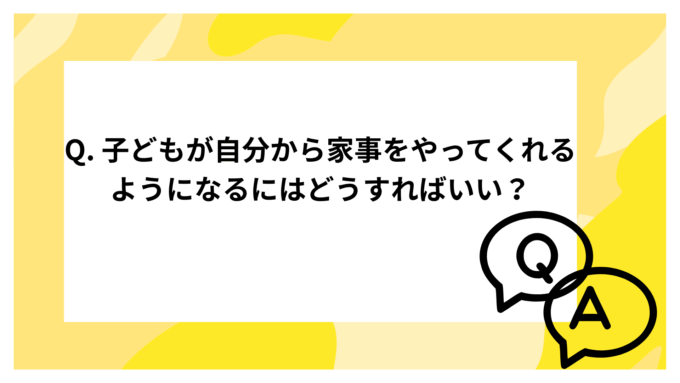


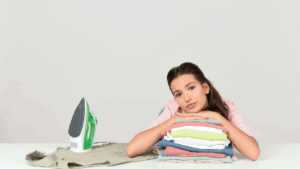
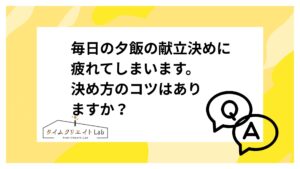
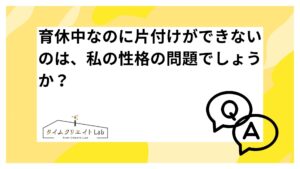
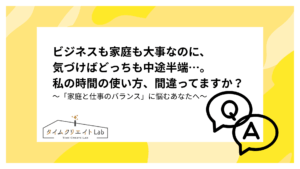
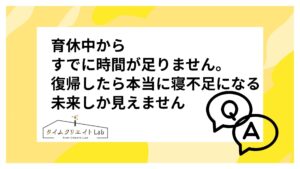
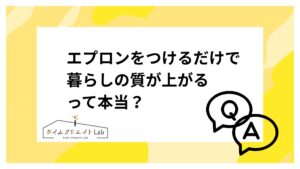
コメント